-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
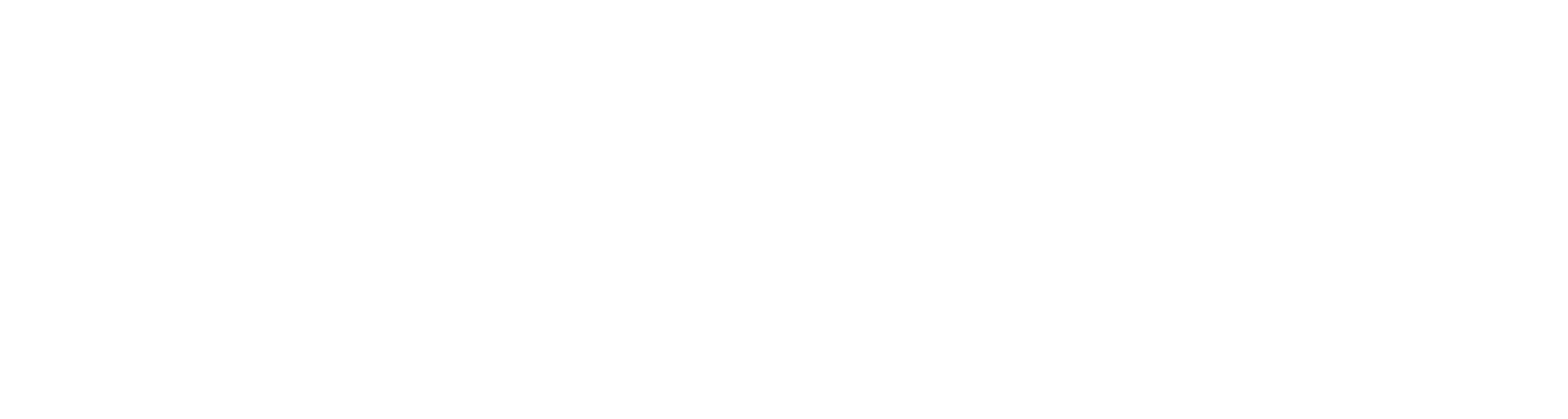
皆さんこんにちは!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っている
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
砕石を敷いたあとは、いよいよ**転圧(てんあつ)**の出番です。
この工程は、「地盤を固めて、沈下や亀裂を防ぐ」ための最重要ステップ。
見た目には地味ですが、建物の耐久性や安全性を決める、まさに**最後の“地盤の仕上げ”**です。
地面の中には、目に見えない“空気の隙間”が無数にあります。
そのまま建物を建ててしまうと、荷重によって地盤が沈み、建物が傾く恐れがあります。
転圧作業では、この隙間を機械の力で圧縮し、地盤を密に締め固めます。
「地盤を固める=未来を守る」
転圧職人は、地中の安定を“音と感覚”で判断するスペシャリストです。
砕石が乾きすぎていると、うまく締まりません。
適度に水をまいて、粒子同士の摩擦を減らすことで密着性を高めます。
プレートコンパクター、ランマー、振動ローラーなどを使用し、
地盤全体を均等に締め固めていきます。
同じ場所を重ねて何度も通すことがポイントです。
締め固めるたびに、レベル測量で高さをチェック。
沈みすぎた箇所は再び砕石を補い、再転圧します。
この“確認と再施工”を何度も繰り返すことで、完璧な地盤が完成します。
「音でわかるんだ、締まったかどうか。」
ベテラン職人の耳は、地盤の“鳴き”を聞き分けます。
ランマー(タンパー):狭い場所での局所的な締め固め
プレートコンパクター:住宅地・外構の砕石層転圧に最適
振動ローラー:道路・造成など広範囲の地盤に使用
機械選びは現場の規模・地質・作業スペースによって変わります。
間違った機械を使うと、締めムラや振動被害が出るため、経験が問われる工程です。
転圧作業では、重機の振動・騒音・粉じんが発生します。
そのため安全対策も徹底。
防塵マスク・耳栓の着用
作業範囲への立ち入り制限
周囲への声かけ・合図の徹底
現場では「ヨシッ!」の掛け声で、確認・報告・連携を欠かしません。
「現場のチームワークが、安全で強い地盤をつくる。」
一人ひとりの気配りが、全体の完成度につながります。
転圧の仕事は、“建物の安全を裏で支える最後の砦”です。
一見単純な作業のようでいて、地盤の硬さ・水分・気温・機械の重さ……
すべての条件を見極めて最適に仕上げる、まさに感覚と理論の融合した職人技。
あなたが押し固めたその一面が、
数十年先まで人の生活を支える地盤になる。
そんなスケールの大きさと責任感を持てる仕事です。
未経験でも、転圧の音・振動・感触を肌で覚えるところからスタート。
「最初は分からなくても、現場が教えてくれる」――それがこの世界の魅力です。
砕石敷きで“均し”、転圧で“固める”
地盤の強度は、建物の寿命を左右する
職人の経験と勘が、現場を支えている
「地面の下の努力が、未来の上に立つ。」
その言葉を胸に、今日も転圧機の音が響いています。
次回もお楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っています。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っている
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
建物の基礎を支える“地盤づくり”。
その中でも「砕石敷き」は、建設の最初に行われる最も重要な下地工事の一つです。
地面の上に砕石(さいせき)を均等に敷き詰め、
これから建つ建物をしっかりと支える“力の受け皿”を整える。
それは、まるで家づくりの“心臓”を形づくるような工程です。
「完成したら見えなくなる部分こそ、いちばん丁寧に。」
それが砕石工事の鉄則であり、職人たちの誇りです。
砕石敷きとは、地面を掘削・整地したあとに、一定の厚みで砕石を敷き詰める作業です。
この層は「路盤」や「基礎下地」と呼ばれ、建物や舗装の重量を分散し、沈下を防ぐ役割を果たします。
砕石には、粒の大きさが均一なクラッシャーランや、
細かい粉を含んだM-40砕石などが使われます。
地盤の硬さや用途に応じて種類を選定するのも、職人の経験と判断力の見せどころです♂️
砕石敷きの目的は単なる“地面の平ら出し”ではありません。
そこには、次のような多機能な役割があります
地盤の安定化:
地表面の弱い部分を補強し、建物全体をしっかり支える。
排水性の確保:
雨水を地中へ浸透させ、建物の下に水がたまるのを防ぐ。
構造物の基礎を守る:
コンクリートが直接地面に触れないようにし、湿気や凍害から守る。
高さ調整・仕上げ基準:
基礎コンクリートのレベル(高さ)を決める上での基準面をつくる。
このように砕石は、構造的にも環境的にも欠かせない存在なのです。
砕石敷きの工程は、シンプルに見えて緻密な技術の積み重ねです。
まず、設計図に合わせて地盤を掘り下げ、余分な土を取り除きます。
地盤の高さを正確に出すため、レーザーレベルでミリ単位の測定を行います。
ダンプトラックで砕石を搬入し、所定の厚み分を敷き広げます。
広げる際はバックホウやレーキ(トンボ)を使い、ムラなく均一に整えるのがポイント。
ここで登場するのが職人の感覚。
「目で見て、足で感じる」微妙な段差を、手作業で丁寧に調整していきます。
この“人の技”が、後の転圧・基礎精度を左右します。
仕上げた砕石層を、次の「転圧」工程でしっかり締め固めるため、
表面を整え、凹凸や石の偏りがないように確認します。
「整地が美しい現場は、仕上がりも美しい。」
そんな言葉が現場ではよく使われます。
砕石敷きには、用途に合わせた機械・道具を使い分けます。
バックホウ(ユンボ):砕石の敷き広げや微調整
レーキ・スコップ:人力での細部修正
レベル(測量機器):高さ基準の確認
ダンプトラック:砕石の搬入
機械作業と人の技が一体となって、初めて美しく正確な砕石面が完成します。
砕石敷きの仕事は、建築の第一歩を担う重要なポジションです。
作業は地味に見えるかもしれませんが、実際は経験と集中力が必要な緻密な仕事です。
「地盤をつくる職人=街を支える職人」
あなたが整えた地盤の上に、建物が建ち、家族の暮らしが始まり、街ができていきます。
これほどやりがいのある仕事は、なかなかありません。
未経験の方でも、先輩が測量の使い方から砕石の厚み調整まで丁寧に教えてくれます。
重機オペレーターを目指す道もあり、キャリアの幅が広いのも魅力です✨
砕石敷きは、“見えない仕事”の中でも最も尊い仕事。
あなたの一日が、未来の建物を支えています。
次回もお楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っています。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っている
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
〜“目には見えない品質”を守る最終チェック〜
掘削工事が終わったあと、すぐに基礎工事が始まるわけではありません。
その前に必ず行われるのが「床付け確認(とこづけかくにん)」です。
これは、掘削した地盤の状態が設計通りで、建物を支えるのに十分な強度を持っているかを確認する最終工程です。
たとえ見た目がきれいでも、地盤が軟弱ならすべてやり直し。
まさに、「現場の命運を握る瞬間」なのです。
床付け確認の主な目的は以下の3つです👇
1️⃣ 掘削深さが設計図通りであるかを確認
2️⃣ 掘削底の地盤が安定しているかを確認
3️⃣ 湧水・軟弱層など、施工に影響を与える要因がないかを確認
この確認をクリアして初めて、「捨てコンクリート(捨てコン)」を打設することができます。
つまり、基礎工事のスタートラインに立つための最終チェックというわけです。
1️⃣ 測定と記録
レーザーやレベル測定器を使い、設計基準面からの高さを正確に測定します。
数ミリ単位での誤差も許されないため、慎重な作業が続きます。
2️⃣ 地盤の目視・触診確認
監督員が地盤を踏んで感触を確かめたり、スコップで表面を掘って状態を確認。
湿り具合や土の締まり具合を五感で判断します👣
3️⃣ 湧水・軟弱層のチェック
もし掘削底に水が溜まっていればポンプで排水し、
軟弱な層があれば掘り直して砕石などで補強します。
4️⃣ 最終確認・写真記録
地盤状態を写真に残し、監督や設計者が立ち会って「合格」を出します。
床付け確認の日、現場はピリッとした緊張感に包まれます。
監督員、測量員、施工管理者が全員で掘削底を囲み、慎重に数値を読み取ります。
ほんの数センチの違いが、建物全体の高さや排水勾配に影響するため、
誰もが真剣そのもの。まさに「現場の技術が試される瞬間」です💥
床付け確認の現場では、技術と責任感が問われます。
でも、そこにこそ職人としての誇りとやりがいがあります。
未経験の方でも、まずは先輩の補助として測量器を扱ったり、
掘削底を整える作業から始めることができます。
現場で学ぶことは多く、最初は緊張の連続かもしれませんが、
数年後にはあなたも監督として、**「この地盤ならOKだ」**と判断できるようになる。
それがこの仕事の面白さであり、成長を実感できる瞬間です🌱
床付け確認は、建物の「強さ」と「信頼性」を保証するための最終関門です。
ここでの判断が正確であるほど、その後の施工はスムーズに進み、
完成後の品質にも直結します。
🌍 掘削工事が“形”をつくる仕事なら、
床付け確認は“品質”を守る仕事。
そして、どちらも欠けては建築は成り立ちません。
一つひとつの確認が、未来の建物の安全を支えている。
それがこの仕事の誇りであり、現場に立つ人々の使命です。
次回もお楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っています。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っている
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
〜地面の下にこそ、“建物の強さ”が宿る〜
建築現場で最初に行われる大規模な工程のひとつが「掘削工事(根切り)」です。
これは、建物の基礎を築くために、設計で定められた深さまで地面を掘り下げる作業。
見た目には地味でも、建築のすべてを支える“最も重要なスタート”なのです。
建物を建てるとき、地表近くの土は柔らかく、時間とともに沈下する恐れがあります。
そのため、安定した地盤層(支持層)まで掘り下げ、そこに基礎を据える必要があります。
この作業を「根切り」と呼び、建物の“足腰”を強くするために欠かせません。
特に大型建築物では、掘削の深さが5〜10メートルを超えることもあり、
その分だけ精密な施工管理と安全対策が求められます。
掘削工事は以下の手順で進められます
1️⃣ 位置出し・測量
設計図をもとに、建物の配置と深さを現場に正確に反映させます。
この段階のミスは、後の基礎工事に致命的な影響を与えるため、慎重さが求められます。
2️⃣ 重機による掘削
バックホウ(ショベルカー)を使用し、指定深度まで丁寧に掘り進めます。
掘削中は、監督や測量員がこまめにレベルを確認し、深さを微調整します。
3️⃣ 土留めの設置
深く掘るほど、周囲の土圧が強くなります。
崩壊を防ぐために「山留め(やまどめ)」と呼ばれる仮設構造物を設置。
H鋼や矢板を組んで、作業員と重機を安全に守ります。
4️⃣ 底面の整地
設計深度に達したら、底面を水平に均し、不要な土を除去。
ここまでの作業で、ようやく「床付け確認」に進む準備が整います。
現場は天候や地質の影響を大きく受けます。
雨が降れば地盤がぬかり、重機が滑る。乾燥すれば粉塵が舞う。
自然との戦いの中で、安全と精度を両立させるのが現場職人たちの腕の見せ所です
また、掘削中に地中障害(古い基礎・配管など)が出てくることもあります。
そのたびに監督や職長が判断し、臨機応変に対応していく。
そこには、経験と判断力、そしてチームの連携力が求められます。
掘削工事の魅力は、「建物の始まりを自分の手でつくる」という実感にあります。
完成した建物の姿は地上にあっても、その基礎はあなたの仕事が支えている。
未経験からでも始めやすく、重機オペレーターや測量補助など、
多様なポジションでキャリアを積めるのがこの業界の強みです
「地面を掘る」と聞くと単純に思えるかもしれませんが、
そこには緻密な測量技術・安全管理・施工精度が集約されています。
“掘る”ことこそが建築の第一歩。
その責任と誇りを感じられるのが、掘削工事の仕事です✨
掘削工事は、建築の“見えない部分”をつくる仕事。
でも、見えないからこそ最も重要で、失敗が許されません。
正確さ・安全・チームワーク。
この3つを徹底して守ることで、次の「床付け確認」や「基礎工事」がスムーズに進行します。
地面の下で行われるこの作業が、やがて人々の暮らしを支える建物へとつながる──
それが掘削工事のやりがいであり、誇りです️✨
次回もお楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っています。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っている
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
設計図の確認が終わったら、現場で最初に行う具体的な作業が 丁張り(ちょうはり) です。
丁張りは、建物の位置や高さを示す基準線を現場に設ける工程で、建物を「正しい場所・正しい高さ」で建てるための道しるべになります。
工事のスタートラインともいえる重要な作業です。
建物の位置決め
設計図に従い、建物が敷地のどこに建つのかを正確に示す。境界からの距離を間違えると、隣地とのトラブルや違法建築につながる恐れがあります。
高さの基準出し
床や基礎の高さを決定し、建物全体の水平を確保する。基準がズレると、完成後に床の傾きや排水不良が発生することがあります。
施工の目印
掘削や基礎工事の際、職人が迷わず作業できるようにする。現場全員が同じ基準を共有することで、工事の精度が向上します。
境界と基準点の確認
測量士や監督が、敷地境界を正しく把握します。
杭打ち
敷地に木杭を打ち込み、横板を渡して枠を作ります。
基準線の設定
水糸やレーザーレベルを使って直線・水平を出します。
最終チェック
設計図と照らし合わせ、誤差がないか再確認します。
環境条件への対応
斜面地や軟弱地盤では杭の高さを調整して水平を確保。
天候の影響
雨風で杭や糸がズレるのを防ぐため、補強を施す。
長期間維持
工事中に基準が消失しないよう、定期点検を行う。
現場では「丁張りがズレれば建物もズレる」という意識を全員が持ち、慎重に作業を進めます。
丁張りは、建物の位置と高さを現場に示す「目に見える基準」です。
建物を正しい場所に建てるための必須工程
水平・直角・高さを精密に決定
その後の基礎工事・上棟作業の品質を左右する
建物が正しく立ち上がるかどうかは、この丁張りの精度次第。つまり、建築工事の成功は「見えない線をどれだけ正確に引けるか」にかかっているのです。
次回もお楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っています。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っている
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
建築工事のスタート地点で最も大切なのが 設計図の確認 です。
設計図は、建物の姿・性能・構造を細部まで表す「工事の青写真」であり、現場の職人や監督が同じ方向を向いて作業を進めるための共通言語となります。
ここでの確認作業を疎かにすると、後の工事全体に影響を及ぼすため、時間をかけて徹底的に行うことが求められます。
基礎形状のチェック
建物を支える基礎は「布基礎」「ベタ基礎」など種類があります。敷地の地盤状態や建物の規模に合わせて正しく設計されているかを確認します。基礎の形状を誤ると、不同沈下や耐震性低下の原因になりかねません。
配筋計画の精査
鉄筋は建物の骨格を守る重要な要素。鉄筋の径・本数・配置間隔・重ね継手の位置などを確認します。もし鉄筋が不足していたり配置が間違っていると、完成後に建物の強度が不足し、耐震基準を満たせなくなる恐れがあります。
寸法の整合性
設計図上の寸法と実際の敷地条件を細かく照合します。数センチの誤差でも、柱や壁、屋根の施工精度に影響を与えます。建物全体の水平・垂直が乱れると、内装や設備の取り付けにも不具合が生じるため、最初の段階で必ず修正します。
設計図の確認は、設計者だけでなく施工管理者や現場の職人も加わり、 多方向からのダブルチェック を行います。
設計者:設計意図や構造的な根拠を説明
施工管理者:施工可能性や安全性を検討
職人:実際に作業する視点からの意見を反映
この連携により、机上の図面と現場の実情をすり合わせ、ミスや不整合を未然に防ぎます。
設計図確認を徹底しないと、以下のようなトラブルにつながります。
基礎の位置ズレ → 建物が敷地境界をはみ出す
配筋不足 → 耐震性が落ち、重大な事故のリスク
寸法誤差 → サッシやドアが収まらず、工期遅延
つまり、設計図確認は「トラブルを未然に防ぐ保険」であり、工事をスムーズに進めるための出発点なのです。
設計図の確認は、建築工事の精度を守る最初の要です。
基礎形状・配筋計画・寸法を丁寧に照合
設計者・監督・職人が連携して確認
手戻りやトラブルを防ぐための重要工程
工事の品質は、この最初の設計図確認にどれだけ真剣に取り組むかで決まるといっても過言ではありません。
次回もお楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っています。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っている
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
地盤改良とは、建物を建てるために土地を強くし、沈下や倒壊のリスクを防ぐ施工のことです。
調査結果で「軟弱地盤」と判断された場合に行われ、建物の規模や地盤の深さに応じて工法が選ばれます。
地表から2m程度までの浅い軟弱層を対象に行います。
土にセメント系固化材を混ぜ込み、地盤を固める方法です。
メリット:コストが比較的安い
デメリット:深い軟弱層には適用できない
主に戸建住宅や小規模建築に用いられます。
地中に穴を掘り、セメントミルクを流し込みながら攪拌し、柱状の改良体を作る工法です。深さ2~8m程度の地盤改良に使われます。
メリット:支持力が高く、幅広い地盤に対応可能
デメリット:工事費用が表層改良より高い
住宅だけでなく、アパートや中規模建築でも選ばれる工法です。
さらに深い支持層に到達させるために鋼管杭を打ち込み、建物を支える方法です。
メリット:非常に高い支持力を確保できる
デメリット:費用が高額、施工時の騒音や振動が大きい
マンションや大型建築など、重量のある建物でよく採用されます。
工法は次の要素を考慮して決まります。
建物の規模(木造住宅かマンションか)
地盤の深さと固さ
工事予算
地盤改良は「とりあえず強くすれば良い」というものではなく、過剰な改良はコスト増につながり、不十分な改良は安全性に欠けるため、バランスが重要です。
環境配慮:セメントを使用するため、地下水や周辺環境への影響を考える必要がある
将来の解体工事:改良杭が残ることで解体時に影響する場合がある
専門家の判断:設計士・地盤調査会社・施工業者が連携して適切に決定
基礎工事は「地盤調査」から始まり、「必要に応じた地盤改良」を経て進められます。
調査と改良は見えない部分の工事ですが、建物全体の安全性を左右する最重要工程です。
調査で現状を把握すること
改良で弱点を補強すること
この2つを丁寧に行うことで、安心して暮らせる住まいの土台が完成します。
次回もお楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っています。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っている
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
建物は、見える部分である柱や屋根だけでなく、見えない「基礎」がしっかりしていなければ長く安心して暮らすことはできません。
基礎工事は、建物の荷重を地盤に伝え、地震や風雨に耐えられる土台をつくるための極めて重要な工程です。
日本は地震が多く、さらに雨や台風による影響も大きい国です。
そのため、基礎工事の質次第で建物の寿命や安全性が大きく変わります。
基礎工事は「設計図の確認」や「丁張り」などから始まりますが、その前に必ず行われるのが地盤調査です。
どんなに強固な基礎を作っても、支える地盤そのものが弱ければ意味がありません。
地盤調査とは、建物を建てる土地の強さや性質を調べる工程です。
代表的な調査方法に**スウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)**があります。
この試験では、鉄のロッドにおもりを乗せ、回転させながら地面に貫入させていきます。
どれくらいの荷重や回転数で地盤に刺さっていくかを測定し、その土地が建物を支える力を持っているかどうかを判断します。
メリット:コストが比較的安く、住宅規模の建物では広く用いられる
調査できる範囲:およそ10m前後の深さまで可能
調査結果は「N値」と呼ばれる指標や、地盤の硬さ・柔らかさ、層ごとの状態として数値化されます。
地盤調査をしないまま建築を進めると、以下のようなリスクが生じます。
建物が傾く(不同沈下)
雨水や地下水による沈下
地震時に揺れが大きくなる
こうしたトラブルは、修繕に莫大な費用がかかり、場合によっては建て直しを余儀なくされます。
調査段階で土地の弱点を把握し、対策を打っておくことが将来の安心につながるのです。
地盤調査の結果、十分な支持力があると分かれば、そのまま基礎工事に進みます。
しかし、もし軟弱地盤と判明した場合は**「地盤改良工事」**が必要です。
次回は、実際の地盤改良の方法や注意点について詳しく解説していきます。
次回もお楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っています。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っている
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
基礎工事と聞くと、「地味」「昔から変わらない作業」なんてイメージを持っていませんか?
実は今、基礎工事はとんでもない進化を遂げようとしています!
キーワードは「環境配慮」と「デジタル化」。
今回は、未来の基礎工事の姿を一般的な市場での例を基にのぞいてみましょう。
従来のセメントよりCO₂排出を大幅に減らせる「低炭素コンクリート」や、産業副産物(スラグやフライアッシュ)を使ったエコ材料の導入が進みそうです。
従来のセメント系改良材ではなく、石灰や天然素材を活用した「環境負荷の小さい固化材」の研究も進んでいます。
電動ショベル・電動杭打機が当たり前に。排ガスゼロで周辺の空気もクリーン。
バッテリーシステムの導入で、騒音とCO₂を一気に減らす。
ICT施工(ドローンで測量→3Dモデルで設計→自動制御重機で施工)により、効率アップ&ムダ削減。
AIで地盤解析
過去のデータを使って、最適な工法・材料をAIが提案。
センサーでリアルタイム監視
地盤沈下や振動を常時モニタリングし、環境にやさしい施工が可能に。
廃材リサイクルが当たり前に
解体したコンクリートや固化処理土を次の工事で再利用。
地盤改良土の再資源化
環境を汚さず、むしろ資源として循環する仕組みが生まれる。
未来の基礎工事は、ただ建物を支えるだけじゃありません。
「環境と共生する土台」をつくる仕事へと変わっていきます。
電動重機やAI施工、エコ材料の普及…これからの基礎工事は、まさに次世代型インフラの最前線です。
次回もお楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っています。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っている
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
建物や橋、あらゆる構造物を支える「基礎工事」。
縁の下の力持ちでありながら、普段はあまり意識されない部分ですよね。
でも、この基礎工事、実は環境に大きな影響を与えていることをご存じですか?
今回は、基礎工事がどんな風に環境と関わっているのか、そして今、どんな課題があるのかを一般的な市場での例を基にわかりやすくお話しします。
基礎工事では大量のコンクリートや鉄筋を使います。特にコンクリートの原料であるセメントは、製造過程でかなりのCO₂を排出するんです。「建物が建つまでにこんなに排出してるの!?」と驚く方も多いはず。
軟弱な地盤では「地盤改良」が必要ですが、セメント系固化材を使うことが一般的。このとき発生する六価クロムなどの有害物質が、地下水や土壌に影響を及ぼすリスクもあります。
杭打ち工事や大型重機の稼働による騒音や振動も、近隣住民や自然環境にとっては大きな問題です。「昼間でも窓ガラスが揺れる!」なんて声も珍しくありません。
従来の「打撃式杭打ち」から、静かに回転で杭を圧入する「回転圧入工法」などへのシフトが進んでいます。これで騒音や振動を大幅にカット。
地盤改良で発生する汚泥を、セメントや石灰で処理しやすくする工法や、リサイクル利用する取り組みも増えています。
ディーゼル規制対応の重機や、排ガスを減らすための施工管理が進められています。最近はハイブリッド重機や電動重機も登場!
コストが高い!
環境対策を強化すると、工事コストはどうしてもアップ。発注者との調整が大変です。
再利用が難しい材料
固化処理した土や廃コンクリートの再利用には、まだまだ技術とルールが追いついていません。
現場の脱炭素化
重機の電動化や再生エネルギーの導入は、これからの課題。
基礎工事は建物の安全を守るために欠かせない作業。
でも、その裏側では、環境とのせめぎあいが続いています。
「安全」と「環境」の両立、これがこれからの大きなテーマですね。
次回は、そんな課題をどう乗り越えるのか、未来の基礎工事についてご紹介します!
次回もお楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
埼玉県川越市で基礎工事・外構工事(エクステリア工事)をメインに行っています。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()