-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
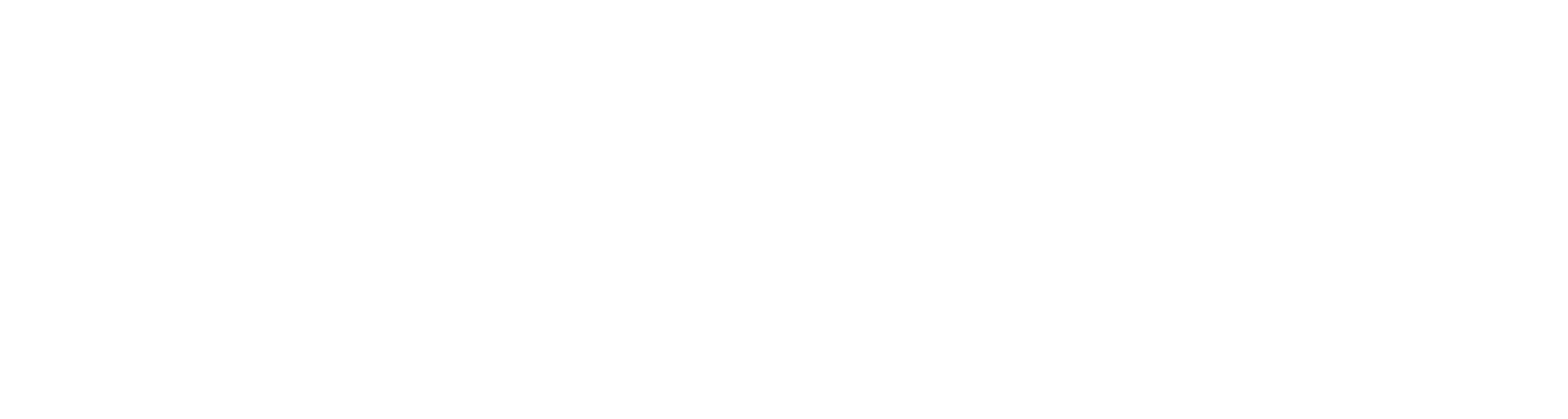
皆さんこんにちは!
埼玉県川越市で基礎工事をメインに行っている
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
〜家もビルも“地面の下”がすべてを決める〜
今回は「基礎工事を成功させるために絶対に守るべき鉄則5ヵ条」をご紹介します。
基礎は、建物の安全・耐久性・性能を左右する“最重要工程”です。
一度完成したらやり直しがきかない――だからこそ、慎重に、確実に、段取りよく進める必要があります。
まず最初の鉄則は、**「地盤調査が全ての出発点」**ということ。
建物の種類や規模に関わらず、以下の調査は必須です:
スウェーデン式サウンディング試験(SWS)
ボーリング調査(中〜大規模)
表層改良や杭工法の要否判断
「なんとなく地盤は大丈夫そう」という感覚で施工すると、不同沈下や構造クラックの原因になります。
調査データをもとに、地盤の特性に合った設計を行うのが鉄則です。
基礎工事の第一歩となる「根切り(掘削)」では、以下の点に注意が必要です:
高低差がないように水平に掘る
雨水や地下水の排水処理(ポンプや暗渠設置)
周囲の崩れを防ぐための山留め(特に深掘りの場合)
ここでの誤差や水対策の失敗が、後の基礎沈下やコンクリートの品質低下を招きます。
**“地面を整える工程こそ職人の腕の見せどころ”**です。
鉄筋コンクリート基礎において、鉄筋は骨そのもの。
以下の点を守ることが強度確保の大前提です。
かぶり厚さ(鉄筋からコンクリートまでの距離)を確保
定着長さ・重ね継ぎ手の規定守る
図面通りの配筋&写真記録で検査に備える
コンクリートに埋めてしまえば見えなくなるからこそ、配筋の精度が信頼の証になります。
コンクリートを型枠内に流し込む作業(打設)では、スピードと均一性が重要です。
ポンプ車の段取りと打設ルートを確認
バイブレーターで気泡を除去し密実化
打設間の時間を空けすぎない(コールドジョイント防止)
特に高温期や寒冷期は、硬化のスピードが極端になるため、養生シートや急結剤の使用など、現場に応じた管理が求められます。
最後の鉄則は「水平と通り(位置)」の正確性です。
ベースや立上がりが傾いていれば、建物全体の傾きや壁のクラックに直結します。
レーザーレベルやトランシットで常時確認
アンカーボルトの位置もミリ単位で調整
打設前に第三者チェック(自主検査)
見えなくなるからこそ、“職人のプライド”が形になるポイントです。
基礎工事は、派手さのない地味な仕事に見えるかもしれません。
しかしその精度と品質が、建物全体の安全性と耐久性を決めることは言うまでもありません。
「正しくつくれば、100年持つ」
そんな言葉が嘘じゃないからこそ、基礎には“職人の誠実さ”が試されます。
この5つの鉄則を守ること――それが、これからも社会の安心をつくり続ける、プロの仕事の証です。
次回もお楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
埼玉県川越市で基礎工事をメインに行っています。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
埼玉県川越市で基礎工事をメインに行っている
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
今回は建築や土木工事の出発点とも言える**「基礎工事の歴史」**をひもといていきます。
建物の安全性や寿命に直結するこの工程――実は、時代とともに驚くほど進化してきました。
普段は見えない部分だからこそ知っておきたい、「地面の下の物語」をご紹介します!
世界最古の基礎工事の記録は、なんと紀元前3000年ごろのメソポタミア文明やエジプト文明にさかのぼります。
当時の神殿や宮殿は、**巨大な石を整地した地面の上に並べて基礎とする「石積み工法」**が主流でした。
地震や地盤沈下への備えはほとんどなく、建物自体が巨大な重量で地面にしっかり座ることで安定を図っていました。
日本でも、古代から中世にかけて**「礎石(そせき)」と呼ばれる石を置き、その上に柱を建てる工法**が広く用いられていました。
有名なのが法隆寺。約1300年前に建てられたこの建物も、礎石の上に柱を立てる形式で、今なお現存しています。
湿気対策としても有効で、地面との間に空間を設けることで通気性を確保し、腐朽を防いでいたのです。
明治以降、西洋建築の影響を受けた日本の建築技術に大きな転換が訪れます。
レンガ・石造・鉄骨建築に対応するために、鉄筋コンクリートと基礎コンクリートの技術が導入されました。
特に昭和に入ると、住宅には以下の2つの基礎工法が普及します。
布基礎:建物の壁や柱の下に帯状に基礎を打つ方式
ベタ基礎:建物全体の下に面でコンクリートを打設する方式
これにより、地盤全体に荷重を分散し、不同沈下を防ぐとともに、シロアリや湿気対策にも有効な基礎が構築されるようになります。
平成〜令和の時代に入ると、地震大国・日本ならではの基礎技術が進化を遂げます。
軟弱地盤には柱状改良・表層改良・鋼管杭打ちによる地盤強化
高層ビルやマンションでは場所打ちコンクリート杭・プレボーリング杭による深基礎
さらに耐震性を高める免震構造(積層ゴムなど)や基礎一体型断熱構造
これらの技術が、現代建築における“強くて長持ちする建物”を下支えしています。
派手な装飾やデザインが目を引く現代建築ですが、本当に重要なのは地面の下――基礎です。
どれだけ美しくても、基礎がダメなら建物は長く持ちません。
時代とともに進化してきたこの基礎工事の歴史は、「安心して暮らすための努力の積み重ね」そのものでした。
次回は、そんな基礎工事において絶対に押さえておきたい「鉄則」を5つご紹介します!
次回もお楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
埼玉県川越市で基礎工事をメインに行っています。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()