-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
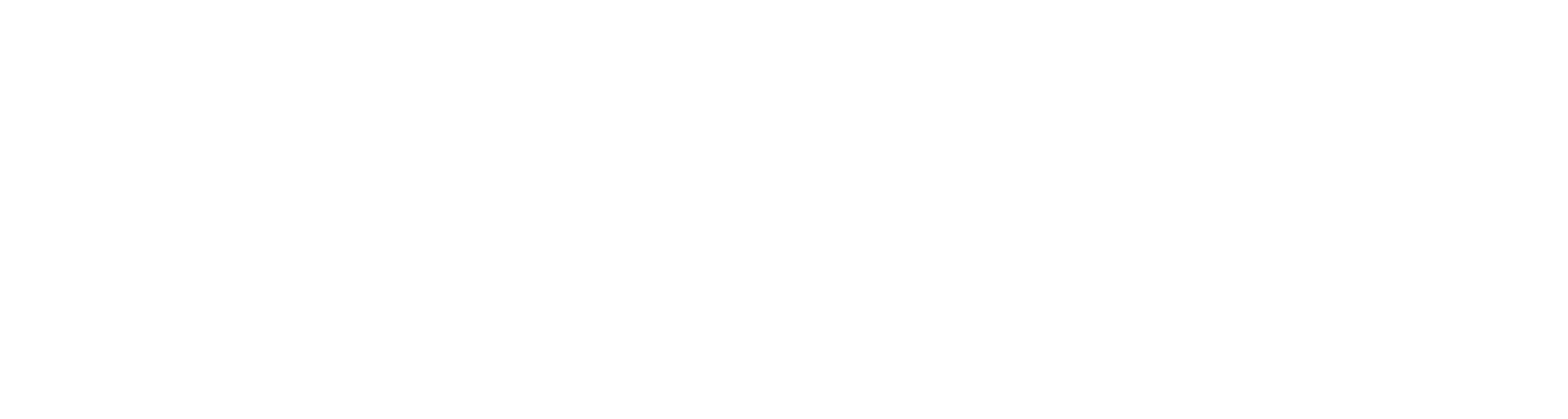
皆さんこんにちは!
埼玉県川越市で基礎工事をメインに行っている
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
目次
〜家もビルも“地面の下”がすべてを決める〜
今回は「基礎工事を成功させるために絶対に守るべき鉄則5ヵ条」をご紹介します。
基礎は、建物の安全・耐久性・性能を左右する“最重要工程”です。
一度完成したらやり直しがきかない――だからこそ、慎重に、確実に、段取りよく進める必要があります。
まず最初の鉄則は、**「地盤調査が全ての出発点」**ということ。
建物の種類や規模に関わらず、以下の調査は必須です:
スウェーデン式サウンディング試験(SWS)
ボーリング調査(中〜大規模)
表層改良や杭工法の要否判断
「なんとなく地盤は大丈夫そう」という感覚で施工すると、不同沈下や構造クラックの原因になります。
調査データをもとに、地盤の特性に合った設計を行うのが鉄則です。
基礎工事の第一歩となる「根切り(掘削)」では、以下の点に注意が必要です:
高低差がないように水平に掘る
雨水や地下水の排水処理(ポンプや暗渠設置)
周囲の崩れを防ぐための山留め(特に深掘りの場合)
ここでの誤差や水対策の失敗が、後の基礎沈下やコンクリートの品質低下を招きます。
**“地面を整える工程こそ職人の腕の見せどころ”**です。
鉄筋コンクリート基礎において、鉄筋は骨そのもの。
以下の点を守ることが強度確保の大前提です。
かぶり厚さ(鉄筋からコンクリートまでの距離)を確保
定着長さ・重ね継ぎ手の規定守る
図面通りの配筋&写真記録で検査に備える
コンクリートに埋めてしまえば見えなくなるからこそ、配筋の精度が信頼の証になります。
コンクリートを型枠内に流し込む作業(打設)では、スピードと均一性が重要です。
ポンプ車の段取りと打設ルートを確認
バイブレーターで気泡を除去し密実化
打設間の時間を空けすぎない(コールドジョイント防止)
特に高温期や寒冷期は、硬化のスピードが極端になるため、養生シートや急結剤の使用など、現場に応じた管理が求められます。
最後の鉄則は「水平と通り(位置)」の正確性です。
ベースや立上がりが傾いていれば、建物全体の傾きや壁のクラックに直結します。
レーザーレベルやトランシットで常時確認
アンカーボルトの位置もミリ単位で調整
打設前に第三者チェック(自主検査)
見えなくなるからこそ、“職人のプライド”が形になるポイントです。
基礎工事は、派手さのない地味な仕事に見えるかもしれません。
しかしその精度と品質が、建物全体の安全性と耐久性を決めることは言うまでもありません。
「正しくつくれば、100年持つ」
そんな言葉が嘘じゃないからこそ、基礎には“職人の誠実さ”が試されます。
この5つの鉄則を守ること――それが、これからも社会の安心をつくり続ける、プロの仕事の証です。
次回もお楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
埼玉県川越市で基礎工事をメインに行っています。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
埼玉県川越市で基礎工事をメインに行っている
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
目次
今回は建築や土木工事の出発点とも言える**「基礎工事の歴史」**をひもといていきます。
建物の安全性や寿命に直結するこの工程――実は、時代とともに驚くほど進化してきました。
普段は見えない部分だからこそ知っておきたい、「地面の下の物語」をご紹介します!
世界最古の基礎工事の記録は、なんと紀元前3000年ごろのメソポタミア文明やエジプト文明にさかのぼります。
当時の神殿や宮殿は、**巨大な石を整地した地面の上に並べて基礎とする「石積み工法」**が主流でした。
地震や地盤沈下への備えはほとんどなく、建物自体が巨大な重量で地面にしっかり座ることで安定を図っていました。
日本でも、古代から中世にかけて**「礎石(そせき)」と呼ばれる石を置き、その上に柱を建てる工法**が広く用いられていました。
有名なのが法隆寺。約1300年前に建てられたこの建物も、礎石の上に柱を立てる形式で、今なお現存しています。
湿気対策としても有効で、地面との間に空間を設けることで通気性を確保し、腐朽を防いでいたのです。
明治以降、西洋建築の影響を受けた日本の建築技術に大きな転換が訪れます。
レンガ・石造・鉄骨建築に対応するために、鉄筋コンクリートと基礎コンクリートの技術が導入されました。
特に昭和に入ると、住宅には以下の2つの基礎工法が普及します。
布基礎:建物の壁や柱の下に帯状に基礎を打つ方式
ベタ基礎:建物全体の下に面でコンクリートを打設する方式
これにより、地盤全体に荷重を分散し、不同沈下を防ぐとともに、シロアリや湿気対策にも有効な基礎が構築されるようになります。
平成〜令和の時代に入ると、地震大国・日本ならではの基礎技術が進化を遂げます。
軟弱地盤には柱状改良・表層改良・鋼管杭打ちによる地盤強化
高層ビルやマンションでは場所打ちコンクリート杭・プレボーリング杭による深基礎
さらに耐震性を高める免震構造(積層ゴムなど)や基礎一体型断熱構造
これらの技術が、現代建築における“強くて長持ちする建物”を下支えしています。
派手な装飾やデザインが目を引く現代建築ですが、本当に重要なのは地面の下――基礎です。
どれだけ美しくても、基礎がダメなら建物は長く持ちません。
時代とともに進化してきたこの基礎工事の歴史は、「安心して暮らすための努力の積み重ね」そのものでした。
次回は、そんな基礎工事において絶対に押さえておきたい「鉄則」を5つご紹介します!
次回もお楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
埼玉県川越市で基礎工事をメインに行っています。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
埼玉県川越市で基礎工事をメインに行っている
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
目次
今回は、基礎工事の現場の1日を時間ごとに追ってご紹介していきます。
「基礎工事の現場ってどんなスケジュールなの?」「どのくらい動いてるの?」という疑問を持っている方に、毎回ではないですが、大体の現場の1日をリアルにお届けします!
作業員が集合するのは、だいたい7時半から8時頃。
まず最初に行うのは、「KY活動(危険予知)」です。
今日の作業内容の確認
使用重機・工具の点検
現場の危険箇所の洗い出し
持病・体調の申告や連絡事項の共有
この時間をしっかり取ることで、“安全第一”の意識が現場全体に浸透します。
午前中は、現場の基礎となる部分の作業を進めます。
この時間は集中力が高く、作業効率も良いゴールデンタイムです。
具体的にはこんな作業が進行します:
ユンボによる掘削
捨てコン打設(作業面の基礎コンクリート)
鉄筋の搬入・加工・配筋作業
型枠の組み立て・微調整
天気のいい日には作業がどんどん進みますが、熱中症や粉塵にも気をつけながら、こまめな水分補給も忘れずに!
待ちに待ったお昼タイム。
お弁当を広げて、仲間と談笑したり仮眠を取ったりと、心と体のリフレッシュタイムです。
現場によっては近くの定食屋に行ったり、車で休憩する人もいます。
この時間の「雑談」からチームワークが深まることも多いんですよ。
午後の作業は、午前中に準備した作業を仕上げる工程です。
型枠完了後、生コン車&ポンプ車到着
コンクリート打設スタート
バイブレーターで気泡を抜き、強度確保
検査員立会いの中間検査、かぶり厚・寸法の確認
残材の撤収・場内清掃
打設中は緊張感が走ります。失敗が許されない作業だからこそ、みんなで声を掛け合いながら慎重に進めます。
すべての作業が終わったら、使用した工具や資材の片付け、現場の清掃を行います。
それが終わると、各自で作業日報を記入したり、翌日の段取り確認。
「一日一日を丁寧に積み重ねる」
これが、現場の品質にも直結します。
基礎工事の現場は、1日中動きっぱなし!ですが、その分、完成時の達成感とやりがいは格別です。
次回は「基礎工事に必要な資格とスキル」をテーマに、どうすればプロになれるのかをご紹介します!
次回もお楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
埼玉県川越市で基礎工事をメインに行っています。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
埼玉県川越市で基礎工事をメインに行っている
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
目次
今回は、私たちの基礎工事の現場に欠かせない**“重機”**について、たっぷりご紹介します。
人の手だけではどうにもならないことも、重機の力があればスムーズに、安全に、そして正確に進めることができます。
現場で活躍する重機にはそれぞれに役割と特徴があり、「この機械がなかったら工事は進まない」と断言できるほど重要な存在なんです。
「掘る」と言えばこれ!基礎工事の現場では最も使用頻度が高い重機です。
正式には「油圧ショベル」と呼ばれていますが、現場では親しみを込めて「ユンボ」と呼ばれることが多いです。
土を掘る(掘削)
掘った土をダンプに積む
整地して地面を平らにする
とにかく何でもこなす万能選手!
アームの操作一つで、数トン単位の土を動かせるため、作業のスピードと効率が格段に上がります。
ユンボには「バックホウ型」「ホイール式」「クローラ式」など種類もいろいろ。
地形や作業内容に応じて、最適なユンボを使い分けるのもオペレーターの腕の見せどころです!
狭い現場でも小回りが利く、**“走れるクレーン”**とも言える存在です。
大型資材や鉄筋束、型枠部材などを吊り上げて所定の位置に運ぶ作業では、クレーンが大活躍します。
高さのある建築物や深基礎の現場
仮設材や型枠パネルの設置
配筋・配管後の重量物据付
操作には技術が必要で、オペレーターは常に安全とバランスを意識しながら作業します。
誘導員との息の合ったやりとりが事故防止にもつながるので、チームワークが求められる重機です。
コンクリート打設の工程で登場する、回転ドラムが特徴の特殊車両です。
コンクリートは「時間との戦い」。ミキサー車が来るタイミングや打設準備のスピードが合っていないと、作業が滞ってしまいます。
新鮮な状態で現場へ運搬
必要量とタイミングの調整
打設中の品質維持が命
ちなみに、生コンは“打ち始めてから90分以内に完了”が基本ルール。
それだけに、現場の段取り力とミキサー車との連携が非常に重要なのです。
重機を操作するのは、ただの力仕事ではありません。
まるで精密機器を扱うような繊細なコントロールが求められる作業も多く、経験と技術の両方が必要です。
資格や講習だけではなく、「現場での実践経験」が何よりの教科書。
ベテランオペレーターの動きには、“ブレ”がありません。
どのくらい掘るか?どの位置に置くか?どんな角度でアームを振るか?
すべてが「現場の流れを止めない」ための大切な判断です。
重機は、基礎工事の現場を支える“縁の下の力持ち”でありながら、ある意味で「主役」と言える存在。
これから工事の世界を目指す人も、重機を知れば、現場の見え方がきっと変わりますよ!
次回もお楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
埼玉県川越市で基礎工事をメインに行っています。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
目次
~建築の足元が、未来を支える~
今回は、建築業界の基盤を支える**「基礎工事」**について、近年の技術革新や注目のトレンドをご紹介します。
基礎工事は、建物を「地面に安全かつ長期的に固定する」ための最も重要な工程です。
地震の多い日本においては、耐震性能の確保はもちろん、環境対応、コスト削減、省施工化なども重要視されるようになり、今、大きな変化が訪れています。
日本では過去の震災を経て、建物に求められる耐震性能が年々高まっています。
これに応じて、基礎工事にもさまざまな耐震技術が導入されるようになりました。
建物と基礎の間に積層ゴムやスライド機構を挟むことで、地震の揺れを建物に直接伝えない構造です。
公共施設・病院・重要インフラ建物に多く採用されています。
基礎内部や構造体に**ダンパー(制震装置)**を組み込み、地震の揺れによる振動エネルギーを吸収。
鉄骨造・RC造との組み合わせで、コストと性能のバランスが取れるとして注目されています。
液状化対策や不同沈下対策として、地盤改良+基礎工法の最適組み合わせも広く導入されています。
表層改良・柱状改良・鋼管杭など、地盤の状態に応じた選択が重要です。
環境配慮は、基礎工事の分野でも例外ではありません。
カーボンニュートラル、廃材の再利用、省資源化といった視点が、設計段階から求められるようになっています。
CO₂排出量の多い通常のポルトランドセメントに代わり、スラグ系・フライアッシュ系の低炭素型セメントを使った基礎が普及。
耐久性も向上し、持続可能な基礎構造として評価が高まっています。
産業副産物(製紙スラッジや鉄鋼スラグなど)を地盤改良材として再利用する動きも。
施工性・安全性を維持しながら、環境負荷を大きく軽減できる技術です。
近年は、ベタ基礎の最適化やスラブ一体化設計によって、不要な掘削や過剰配筋を抑える設計手法も広がっています。
人手不足や技能者高齢化の問題を背景に、デジタル技術・自動化機械の導入も着実に進んでいます。
GPS・3Dスキャナを使った正確な地盤計測・施工精度の可視化
タブレットでの配筋・レベル管理のリアルタイム確認
ドローンによる施工前後の撮影・記録管理
これにより、現場管理の効率化・記録性向上・手戻りの削減が可能に。
配筋自動ロボット
型枠の自動組立システム
地盤改良機へのAI搭載で、最適な攪拌速度や施工深度を自動設定
これらはまだ一部の大規模現場での導入に限られますが、今後は中小規模の住宅基礎にも広がる可能性があります。
基礎工事は、建物の構造を「見えない場所」で支える大切な役割を担っています。
しかし今やその技術は、単なる“支持力”だけでなく、
耐震性
環境性能
省力化・省施工性
ライフサイクルコスト最適化
といった、これからの建築に必要な要素を最前線で支える分野へと進化しています。
基礎工事に「新しさ」を感じたのは、久しぶりだと思った方も多いのではないでしょうか?
新築・増改築・工場建設など、どのプロジェクトにおいても、最適な基礎の選定は成功の第一歩です。
ご相談や導入に関するお問い合わせはいつでも受け付けております。
現場の条件や規模に応じて、最適な基礎工事のご提案が可能です。
次回は、**「地盤調査から見る基礎設計のコツ」**を予定しています。
基礎工事と密接に関わる“調査と診断”の視点から、設計・施工をもっとスムーズにするヒントをお届けします。
どうぞお楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
シリーズ3: 基礎工事でよくあるトラブルと対策!
~失敗しない基礎工事のポイント~
前回のシリーズ2では、基礎工事の流れ を詳しく解説しました。
基礎工事は、建物を支える重要な工程ですが、施工の不備や地盤の問題によってトラブルが発生することもあります。
今回は、基礎工事でよくあるトラブルとその対策について詳しくお話ししていきます!
1. 基礎が沈んでしまう「不同沈下」
不同沈下とは?
不同沈下(ふどうちんか)とは、建物が均等に沈まず、一部だけ沈んでしまう現象 のことです。
家が傾くことで、以下のような問題が発生します。
✅ ドアや窓が閉まりにくくなる → 建物が歪むため、開閉がスムーズにできなくなる。
✅ ひび割れが発生する → 壁や基礎部分にクラック(ひび)が入る。
✅ 床が傾いてしまう → 体感できるほどの傾斜ができることも。
不同沈下が起こる原因
✅ 地盤が弱い → もともと軟弱な地盤の上に建てられた場合、支えきれずに沈んでしまう。
✅ 地盤改良が不十分 → 適切な補強工事が行われていないと、時間が経つにつれて沈下することがある。
✅ 基礎の設計ミス → 荷重のかかり方を考慮せずに基礎を施工すると、バランスが崩れてしまう。
不同沈下の対策方法
✅ 地盤調査をしっかり行う → 事前の調査で、地盤の強さをしっかり確認する。
✅ 必要に応じて地盤改良を実施 → 砕石やセメントを使って地盤を強化する。
✅ 基礎の設計を適切に行う → 重心のバランスを考慮し、沈下しにくい基礎を設計する。
不同沈下は、一度発生すると修復が困難で、高額な補修費用がかかるため、事前にしっかりと対策することが重要 です。
2. 基礎にひび割れが発生する
ひび割れの種類
✅ 構造的なひび割れ → 建物の荷重や地盤の動きによって発生する大きなひび割れ。
✅ 乾燥収縮によるひび割れ → コンクリートが固まる際の収縮によって発生する小さなひび割れ。
ひび割れの原因
✅ コンクリートの乾燥が早すぎる → 急激な温度変化や直射日光が原因。
✅ 鉄筋の配置が不適切 → 強度を確保できず、ひびが入りやすくなる。
✅ 地盤の沈下 → 建物の一部が沈むことでひび割れが発生する。
ひび割れを防ぐ対策
✅ コンクリートを適切な条件で養生する → 乾燥しすぎないように水をまいて管理する。
✅ 鉄筋の配置を適切に行う → 構造計算をしっかり行い、強度を確保する。
✅ ひび割れ補修を早めに実施 → 小さなひびでも、放置せずに早めに補修する。
ひび割れが放置されると、雨水が侵入し、基礎の劣化が進む ため、早めの対応が大切です。
3. コンクリートの強度不足
コンクリートの強度が不足すると?
基礎のコンクリートに十分な強度がないと、以下のような問題が発生します。
✅ 基礎の耐久性が低くなる → 地震や台風時に破損するリスクが高まる。
✅ ひび割れが発生しやすい → 十分に固まらないまま施工すると、強度が確保できない。
✅ 建物全体が不安定になる → 長期的に見ても、安全性が損なわれる。
コンクリートの強度不足の原因
✅ 水分が多すぎる → 水を多く混ぜると作業しやすくなるが、強度が下がる。
✅ 適切な養生が行われていない → コンクリートがしっかり固まる前に乾燥すると、強度が低下する。
✅ 施工時の気温が極端 → 気温が高すぎると急激に乾燥し、低すぎると凍結してしまう。
コンクリートの強度を確保するための対策
✅ 適切な配合でコンクリートを作る → 必要以上に水を加えない。
✅ 打設後の養生をしっかり行う → 温度管理を行いながら、適切な湿度を保つ。
✅ 強度試験を実施する → コンクリートのサンプルを取り、一定期間後に強度を測定する。
4. 地盤改良をしないことで起こるトラブル
地盤が弱いまま基礎工事を進めると、不同沈下やひび割れのリスクが高まります。
適切な地盤改良方法
✅ 表層改良 → 表面の土を固める方法。比較的浅い部分の補強に使用。
✅ 柱状改良 → セメントなどを使い、柱状の補強を行う。
✅ 鋼管杭工法 → 深い地盤まで杭を打ち込み、建物を支える。
地盤改良は、建物の寿命を大きく左右する重要な工程 なので、しっかりとした対策を行いましょう。
まとめ:基礎工事のトラブルを防ぐために
基礎工事のトラブルは、事前の調査や施工の精度を高めることで防ぐことができます。
✅ 不同沈下を防ぐために、事前の地盤調査をしっかり行う
✅ ひび割れを防ぐために、コンクリートの養生を適切に行う
✅ コンクリートの強度を確保するために、水分管理を徹底する
✅ 必要な場合は地盤改良をしっかり実施する
基礎は一度施工すると簡単に修正できない部分 なので、施工の段階で適切な対策を行うことが大切です。
次回予告:基礎工事の最新技術とこれからのトレンド!
次回は、最新の基礎工事技術や、これからの建築業界で注目されている工法について ご紹介します!
✅ 最新の耐震基礎技術とは?
✅ エコな基礎工法が注目されている理由
✅ AIやロボットが基礎工事を変える?
次回もお楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
シリーズ2: 基礎工事の流れを詳しく解説!
~しっかりした基礎をつくるための工程~
前回のシリーズ1では、基礎工事の役割や種類 についてお話ししました。
今回は、実際の基礎工事の流れ を詳しく解説していきます。
基礎工事は一つひとつの工程がとても大切で、丁寧な施工が建物の安全性を大きく左右します。
それでは、基礎工事の工程を順番に見ていきましょう!
1. 地盤調査 – 安定した土地かを確認
基礎工事を始める前に、まず行うのが地盤調査 です。
土地が十分な強度を持っているかを確認し、どの基礎工法が適しているのかを判断 します。
地盤調査の方法
✅ スウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)
一般的な住宅建築でよく使われる調査方法。鉄の棒を地面にねじ込み、地盤の硬さを測定します。
✅ ボーリング調査
ビルやマンションなどの大型建築で行われる方法。地中に穴を掘り、土のサンプルを採取して地層の状態を確認します。
もし地盤が弱い場合は、地盤改良工事を行って強化します。
2. 根切り(掘削工事) – 基礎をつくるためのスペースを掘る
地盤の状態が確認できたら、次は基礎を施工するためのスペースを掘る**「根切り(ねぎり)」** という作業を行います。
根切りのポイント
✅ 基礎の形状に合わせて掘る
布基礎なら建物の外周と主要な柱部分、ベタ基礎なら建物全体を掘る。
✅ 適切な深さまで掘る
地盤の強度や設計図に基づいて、適切な深さまで掘削する。
根切り作業の精度が低いと、後の工程に影響を与えてしまうため、丁寧に作業を進めることが大切です。
3. 砕石敷き・転圧 – 地盤を強化する
掘削が完了したら、次に行うのが砕石(さいせき)を敷いて、地盤をさらに強化する作業 です。
砕石とは?
砕石とは、細かく砕かれた石のこと。
砕石を地盤に敷き詰めて転圧(押し固めること)することで、基礎の安定性を高めます。
✅ 厚さ10cm程度に敷き均す
✅ 振動ローラーやプレートでしっかり転圧
砕石を敷くことで、地面からの湿気を抑え、基礎全体の耐久性を向上させます。
4. 防湿シート設置 – 湿気対策
基礎の耐久性を高めるために、「防湿シート」 を敷く工程も重要です。
なぜ防湿シートが必要?
✅ 地面からの湿気を防ぎ、床下のカビや結露を防ぐ
✅ シロアリ被害のリスクを減らす
防湿シートをしっかりと敷き詰め、隙間ができないように施工します。
5. 鉄筋組み立て – 基礎の強度を確保
ここからは、基礎の骨組みとなる「鉄筋」を組み立てる作業 です。
✅ 鉄筋を格子状に組み、強度を確保
✅ 結束線でしっかり固定し、ずれないようにする
✅ 適切なかぶり厚(鉄筋とコンクリートの距離)を確保
鉄筋の組み方が弱いと、基礎の強度が不足し、ひび割れや劣化の原因 になってしまいます。
6. 型枠設置・コンクリート打設
次に、基礎の形を作るための型枠を設置 し、そこにコンクリートを流し込む「打設」 を行います。
✅ 型枠をしっかり固定する → コンクリートが流れ出さないように、頑丈に組む
✅ コンクリートを均等に流し込む → 隙間ができないよう、バイブレーターで気泡を抜く
✅ 養生(ようじょう)期間を設ける → コンクリートがしっかり固まるまで待つ
コンクリートは打設後すぐには固まらないため、最低でも数日間の養生が必要 です。
7. 仕上げ・基礎完成
コンクリートがしっかり固まったら、最後に仕上げを行います。
✅ 型枠を外す → コンクリートが十分に固まっていることを確認してから型枠を撤去。
✅ 表面をきれいに仕上げる → ひび割れや剥がれがないか確認し、補修。
✅ 建物の土台部分を確認 → 建築工事に入る前に、基礎の状態を最終チェック。
基礎が完成すれば、いよいよ建物の建築工事が始まります!
まとめ:基礎工事は慎重に進めることが重要!
基礎工事は、建物の寿命や安全性を大きく左右する大切な工程 です。
✅ 地盤調査でしっかりと土地の状態を確認
✅ 砕石・防湿シート・鉄筋で耐久性を向上
✅ コンクリート打設は丁寧に行い、しっかり養生する
一つひとつの工程を丁寧に行うことで、地震や台風などの自然災害にも耐えられる、強い建物が完成します。
次回予告:基礎工事でよくあるトラブルと対策!
次回は、基礎工事の現場でよくあるトラブルと、その対策について詳しく解説します!
✅ 基礎が沈んでしまう「不同沈下」の原因は?
✅ ひび割れが発生する理由と防止策
✅ 地盤が弱い土地での対策方法とは?
トラブルを防ぐために知っておきたいポイントをお届けしますので、お楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社戸田土建、更新担当の富山です。
徐々に暖かくなってきましたが、皆さん元気に過ごされていますか?
さて、本日からシリーズ更新が始まります!
記念すべき第1回目のテーマは!
基礎工事とは? 建物を支える大切な役割についてです!
普段はなかなか目にすることのない「基礎工事」ですが、実は建物の安全性を左右する、非常に重要な役割を持っています。
どんなに立派な建物を建てても、基礎がしっかりしていなければ、地震や自然災害に耐えられず、大きなトラブルにつながってしまうのです。
では、基礎工事とは具体的にどんなものなのか、どのような工程で進められるのか、シリーズを通して詳しくお話ししていきます!
1. 基礎工事とは?
基礎工事とは、建物の土台をつくる工事 のことを指します。
建物を支える「足元」を強固にすることで、安定した構造を確保し、地震や風圧などの外的要因にも耐えられる建物を実現します。
基礎工事の主な役割
✅ 建物の荷重を地面に均等に分散する → 一部に荷重が偏ると、地盤沈下やひび割れの原因になるため、基礎は建物全体を均等に支える設計になっています。
✅ 地盤と建物をしっかり結びつける → 地盤の状態に合わせた基礎をつくることで、建物が安全に立ち続けられるようにします。
✅ 地震や台風などの災害に備える → 適切な基礎工事が行われていれば、災害時の揺れにも強い建物が完成します。
2. 基礎の種類
基礎工事には、いくつかの種類があります。
建物の用途や地盤の状況によって、最適な基礎を選ぶことが重要です。
① 布基礎(ぬのぎそ)
布基礎とは、建物の外周や内部の主要な柱の下に、連続したコンクリートの帯(フーチング)を配置する 基礎工法です。
特徴
✅ 比較的コストが抑えられる → 一般住宅などでよく採用される工法。
✅ 施工がシンプルで、工期が短い → コンクリートの使用量が少なく、作業がスムーズ。
✅ 地盤の強度が必要 → 地盤が軟弱な場合には補強が必要になる。
② ベタ基礎(べたぎそ)
ベタ基礎は、建物の底全体を鉄筋コンクリートの厚い板で覆う 方式です。
特徴
✅ 地盤が弱い場所でも対応しやすい → コンクリートが面全体で支えるため、不同沈下(建物が傾く現象)が起きにくい。
✅ シロアリ対策にもなる → 地面をコンクリートで覆うため、シロアリが侵入しにくい。
✅ コストがやや高め → 布基礎よりもコンクリートを多く使用するため、費用がかかる。
③ 杭基礎(くいぎそ)
杭基礎は、地盤が弱い場所に建物を建てる際に、地中深くに杭を打ち込んで建物を支える工法 です。
特徴
✅ 地盤が弱くても高層建築が可能 → ビルやマンションなど、大型の建築物に採用されることが多い。
✅ 揺れに強い → 地盤の深い部分の硬い地層に杭を打ち込むことで、安定性が増す。
✅ 工事費が高い → 専用の重機が必要なため、費用がかかる。
3. 基礎工事の工程
基礎工事は、以下のような流れで進められます。
① 地盤調査 → 土地の強度を確認し、最適な基礎の種類を選定。
② 根切り(掘削工事) → 地面を掘り、基礎を施工するスペースを確保。
③ 砕石敷き・転圧 → 砕石を敷いて地盤を固め、強度を高める。
④ 防湿シート設置 → 地面からの湿気を防ぐため、シートを敷く。
⑤ 鉄筋組み立て → 強度を確保するために、鉄筋を配置。
⑥ コンクリート打設 → 型枠を組み、コンクリートを流し込む。
⑦ 養生・仕上げ → コンクリートが固まるまでしっかり養生し、仕上げる。
まとめ
基礎工事は、建物の安全を支える最も重要な工事のひとつです。
✅ 基礎工事がしっかりしていれば、建物の耐久性が高まる
✅ 地盤に合わせた基礎の種類を選ぶことが重要
✅ 適切な施工を行うことで、不同沈下や災害リスクを減らせる
このシリーズでは、基礎工事の具体的な施工方法や注意点、よくあるトラブルなどについて詳しく解説していきます。
次回予告:基礎工事の流れを詳しく解説!
次回は、基礎工事の具体的な工程をさらに詳しくご紹介します!
地盤調査ってどうやって行うの?
砕石敷きやコンクリート打設のポイントは?
基礎工事で気をつけるべきことは?
実際の施工現場の流れをわかりやすく解説しますので、お楽しみに!
株式会社戸田土建では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()